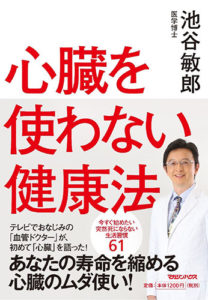病気と歴史 - 正岡子規が脊椎カリエスにならなかったら、政治家として日本を動かしたかもしれない

22歳のときに喀血、政治家への夢を断たれる
司馬遼太郎氏の『坂の上の雲』は、維新を経て近代国家の仲間入りをしたばかりの明治の日本を描いた歴史小説であるが、第1巻は正岡子規と秋山真之など青雲の志を抱いた青年たちを活写した青春小説の趣が強く、とくに子規は魅力ある人物として描かれている。
『坂の上の雲』はテレビドラマ化され、香川照之が子規役を好演したが、好漢子規に日本人の子規人気はいっそう高まったと思われた。
俳人であると同時に歌人でもあった正岡子規は、慶応3年9月17日(1867年10月14日)、現在の愛媛県である伊予の松山で生まれた。本名を常規(つねのり)といい、またの名を升(のぼる)といった。旧制松山中学に入学するが、政治家を志し、中退して上京した。旧制一高の前身である大学予備門に入り、ここで夏目漱石と知り合い2人は終生の友となった。
漱石とはまず、寄席の話で気があったという。子規はまた当時アメリカから入ってきたばかりのベースボールに熱中し、多くの野球用語を邦訳した。その一方で古俳諧の研究を進めたり、友人と一緒に句作にも励んだりしていた。
希望にあふれた若き子規を結核という病気が襲ったのは、明治22年(1889)5月9日、子規22歳のときだった。その翌日には、医者から肺結核と診断されている。自らの号を子規としたのは、この喀血をした直後のことだった。同22年、後に東京帝国大学となる帝国大学文学部哲学科に入学した。政治家になろうと考えていた子規はその夢を捨てたが、それは結核ゆえで、大きな挫折であった。
大学ではのちに日本文学科にうつった。25年(1892)に叔父の紹介で陸羯南の日本新聞社に入社したが、同社は子規終生の職場となった。翌年、新聞「日本」に『獺祭書屋俳話』を連載するとともに『芭蕉翁の一驚』を発表し、妄信的芭蕉崇拝者を痛烈に批判した。
俳句革新を目指していた高浜虚子や河東碧梧桐らと新感覚の句作を続けていたが、29年(1896)に子規のグループは俳壇の一勢力と認められ、日本派と呼ばれるようになった。
俳句、和歌の世界に革新の激震を引き起こす
新聞、雑誌はこぞって日本派の俳句を掲載しはじめ、旧派打倒を目指した子規の志は一応の達成を見た。30年(1897)1月に松山で発刊された『ホトトギス』も翌年からは発行所を東京へ移転し、虚子が編集を担当するようになった。
一方、和歌に関しては、明治30年、32歳の時発表した『歌よみに与ふる書』は「貫之は下手な歌よみにて……」といった鋭い語調で『古今集』を否定し、『万葉集』を高く評価し、当時の歌壇に衝撃を与えた。
これより和歌革新に本格的に着手することになった。しかし、当時は明星派の浪漫主義の新風が人気絶頂であり、子規の主張が歓迎されたとはいい難かった。しかし、門弟からは伊藤左千夫や長塚節が出ている。
日清戦争に記者として従軍。帰途の船中で大喀血をする
このように俳句、和歌の世界に革新の激震を引き起こした子規であるが、俳句を生涯の事業と考えていたのだろうか。子規は28年(1895)には、新聞『日本』の記者として、周囲の反対を押し切って従軍記者として日清戦争の戦地に赴いたが、その帰途の船中で大喀血をした。結核の再発で重篤な状態に陥ったのだった。
須磨で一時保養した後、松山へ帰り、当時松山中学に赴任していた夏目漱石の下宿で静養した。ちなみに、新聞『日本』の発行元・日本新聞社長の陸羯南は、俳人としての子規を育て、生涯を通じて社員として雇い、支え続けた。
子規は、何をしたかったのか。30年に、高浜虚子に向かって、「われほど多き野望を抱いて死ぬ者あらじ」と語り、さらに、「自分の大望に比べれば俳句の仕事などはほとんど零」
とまでいい切っている。遠くない日に生命が尽きることを自覚していたのであろう。
日清戦争への従軍は、子規の病を大きく進ませることになった。28年の10月に再び上京するが、この途中、須磨に到着したとき、歩くこともできないほどの腰痛に襲われた。結核菌が脊椎を侵し、脊椎カリエスを発症したのだった。
それでも須磨でしばらく静養し、痛みがおさまった子規は、奈良まで足を延ばし、「柿食へば鐘が鳴るなり法隆寺」という名句を詠んでいる。
東京に戻って専門医から脊椎カリエスと診断された子規はその後、死ぬまでほとんど病床に釘づけになってしまう。そういう状態の中、前述したような、俳句、和歌に関して旺盛な活動を続けたのだった。
脊椎カリエスで病床に釘付けも、旺盛な創作活動を続ける
その後は脊椎カリエスのために病床に釘づけになるが、旺盛な活動をする。同33年(1901)年、子規35歳のとき、『仰臥漫録』の筆を起こしたが、すでにその肺は左右ともに大半空洞になっていて、医師の目にも生存自体が奇蹟と映ったという。
痛みのために伏せることができないため、仰向けになったまま、日課として、病床での生活を半紙を綴じたものに毛筆で記した。漫録と題しているが、闘病記でもあり、しかし、現在多数出版されている凡百の闘病記や病気体験記、病気克服記とは格段に違う。
痛みと苦痛にうめき、一方で、すさまじいほどの食欲をみせる。一日に食べる量は、とても病人とは思えないほど多い。同35年(1903)からは『病牀六尺』を書き始めたが、麻酔薬が切れ、阿鼻叫喚とも言うべき苦痛にのたうち回り、「誰かこの苦を助けて呉れるものはあるまいか。誰かこの苦を助けて呉れるものはあるまいか」と綴っている。
同年九月、子規は「糸瓜咲て痰のつまりし仏かな」という句を遺して、36年の短い生涯を終えた。
かつて不治の病と恐れられた結核だが、現在では完治できる。結核が見つかった時点で治療をすれば確実に治るし、たとえ脊椎カリエスになっても数年で完治できるはずだ。
もし子規が現代に生きていたなら、結核で死ぬことはないだろう。そうすると、俳句や短歌といった文学の世界には進まずに、政治家になっていた可能性が強い。そうなると、誰が俳句や短歌の近代化をしたのだろうか。
あるいは、政治家になったら、親友秋山真之と政治家、軍人としての接点も生まれたのではないだろうか。政治家として日本を動かしたかもしれない。
文:東/茂由 ライター
1949年、山口県生まれ。早稲田大学教育学部卒。現代医学から東洋医学まで幅広い知識と情報力で医療の諸相を追求し、医療・健康誌、ビジネス誌などで精力的に取材・執筆。心と体、ライフスタイルや環境を含めて、健康と生き方をトータルバランスで多面的に捉えるその視点に注目が集まる。