病気と歴史 - 結核で夭逝しなかったら瀧廉太郎は大音楽家になっていた
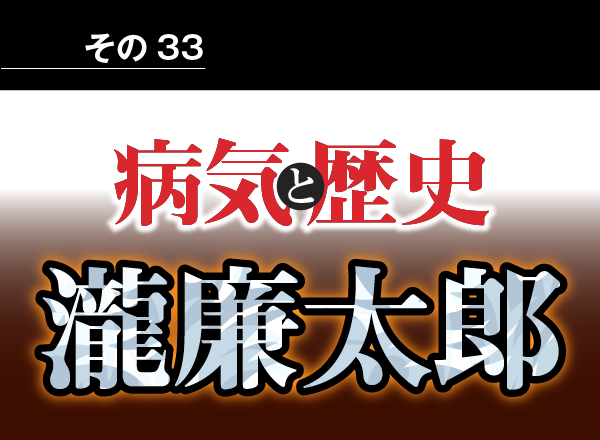
22歳で欧州へ国費留学
明治19年(1886)に東京で生まれた滝廉太郎は、後に東京音楽学校となる高等師範付属音楽学校に在学中から、すでにピアノと作曲の才能を発揮した。明治時代の前半には、翻訳の唱歌がたくさんつくられたが、無理に邦訳の詩をあてはめたものが多かった。廉太郎は日本人による曲作りを初めて行った。
研究科を卒業すると同時に、母校の教師として2年ほど勤務した。彼はテノールの美声に恵まれ、ピアノ演奏にすぐれ、クラリネット奏法も心得ていた。
明治33年(1900)、22歳のとき、日本人の音楽家として2人目となる国費でのヨーロッパ留学生に選ばれた。翌年4月、ドイツに向かって横浜港を発つが、その間の一年は生涯でもっとも多くの作品を残した年であった。『四季』『メヌエット』『幼稚園唱歌』『荒城の月』『箱根八里』『豊太閤』など、今も知られる名曲ばかりである。『メヌエット』は日本人作曲家による初めてのピアノ協奏曲であった。
音楽院に合格も結核に罹患。休学から帰国へ
明治34年(1901)6月、蓮太郎は東部ドイツのライプチヒに到着した。同年10月1日、国立のライプチヒ音楽院の入学試験を受けて合格した。本格的な作曲法を学びはじめたのだが、突然の不幸が振りかかった。遠い異国の地で、当時、不治の病といわれた結核にかかってしまったのである。
11月25日、オペラを見にゆき、それがもとで風邪をひき、病状がこじれてなかなか治らなかった。ライプチヒ在住の日本人たちの勧めで、12月2日、彼はライプチヒ大学病院に入院して療養することになった。結核に罹患したのだった。医者の勧めで、翌年三月まで学校を休学することにし、その手続きをとった。
春になって、快方に向かったように思えたが、入院は続いた。蓮太郎入院の報はもちろん関係者に伝わっていて、3月には巌谷小波と幸田幸が病院に見舞いにきた。幸田幸は、音楽学校の第1回目の留学生だった。
3月には、彼の先生であった島崎赤太郎が4人目の音楽留学生としてドイツに来て見舞った。島崎は蓮太郎の病状をみて、1年前留学出発当時と比較して彼の体力を心配し、滞在中の医学留学生にも相談して、今の小康を得ているときに帰国させたほうではないかと大使館のほうと相談し、その旨母校に報告した。
帰国前、「荒城の月」作詞の土井晩翠と人生一度の出合い
蓮太郎の病状を見たドイツ駐在井上公使は7月4日、外務大臣小村寿太郎宛に蓮太郎の帰国の必要を通告して、これを申請した。
外務大臣はただちに文部大臣宛にその旨を通知し、文部大臣もこれに同意し、そのことを東京音楽学校校長渡辺龍聖に通告した。こうして、蓮太郎の帰国が決まった。
日本への帰船、日本郵船の大型客船若狭丸が8月24日、イギリス郊外のテムズ川河口ティルベリー・ドックに着岸していた。そこへ彼を見舞うため、ロンドン留学中の詩人土井晩翠と宗教学者姉崎正治が訪れた。『荒城の月』を作曲した滝廉太郎と作詞した土井の最初にして最後の出合いだった。
同年10月17日に横浜に到着した。東京にある従兄の滝大吉の家で療養する予定であったが、大吉が脳卒中で急死する不幸に見舞われた。これ以上厄介になることはできないと、廉太郎はすぐに大分県竹田町に向かって立ち、大吉の通夜、葬儀は欠席した。
竹田の実家に帰り、療養を続けたが、治療の甲斐もなく、翌36年(1903)6月29日、父母や弟妹に看取られながら息を引き取った。23歳の夭逝だった。故郷でも作曲を続け、『別れの歌』『水のゆくへ』『荒磯』などを残している。
真に夭折という言葉がふさわしい
海老澤敏著『瀧廉太郎─夭逝の響き』(岩波新書)は、音楽美術、音楽史が専門の著者が廉太郎の音楽について新しい主張を展開している好著である。その1章に「長い間奏曲
夭折音楽家たちの世界」と題した項目がある。そこでは、「35歳で亡くなったモーツアルトも31歳で生涯を閉じたシューベルトも夭折ではなかった」と述べている。
その理由として、モーツアルトについて、当時の平均寿命が短かったこと、30年もの長い歳月を作曲家として過ごし、多くの作品を当時の声楽と器楽のジャンルにわたって生み出し、しかも若い時期の作品も含めて高度の完成度を表していることを挙げている。そして、シューベルトもまた然りである、と。
翻って、廉太郎は、ライプチヒで本格的な修業をはじめたばかりのところで結核に倒れた。最後の作品『憾』は激烈な響きを持っているが、なぜだろうか。同書は、
「作曲家としての前途は、自他ともに、揚々たるものがあると信じられたであろう。だが、その希望に満ちたはずの将来が、無慈悲な病魔によって、まさに一刀両断に断ち切られる。もしそうでなければ彼のいくつかのジャンルにおよぶ声楽曲の創作活動は、ライプチヒでの真剣な懸命な勉学を終えた暁には、祖国日本で存分に展開され、洋楽草創期の絢爛たる花園に、豊かで華やかな無数の大輪の花を咲かせたにちがいない」と書き、さらに次のように続けている。
「その燃えるような希望が、無残にも暴力的に踏み躙られる無念さを、彼、瀧廉太郎はおそらくライプチヒで感じ取っていたことに疑いはない。帰国後、その無念さを、彼は、その分野の演奏においても天才的と評されていたピアノ演奏で、1曲のまこと短いかぎりの楽曲の中に結晶させる。それこそ、彼の白鳥の歌となった『憾』にほかならない」
さぞ無念であっただろうが、薄命だったからこそなお私たち日本人は廉太郎の曲に愛着を覚えるし、その価値はいっそう高まったのだろう。詩の意味をまったく知らない子供のとき、聴いても歌っても魂が揺さぶられたことを覚えている。蓮太郎が夭折したことは、親か学校の先生に教えられた。
私たち日本人は、『荒城の月』を聴くとき、夭逝の悲しみをともにすることができるのであろうか。
文:東/茂由 ライター
1949年、山口県生まれ。早稲田大学教育学部卒。現代医学から東洋医学まで幅広い知識と情報力で医療の諸相を追求し、医療・健康誌、ビジネス誌などで精力的に取材・執筆。心と体、ライフスタイルや環境を含めて、健康と生き方をトータルバランスで多面的に捉えるその視点に注目が集まる。

