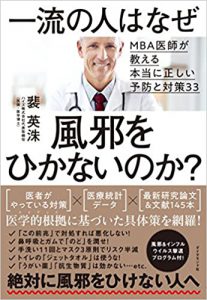病気と歴史 - 胃潰瘍が国民的作家、漱石の『明暗』を未完にさせた(1/3)
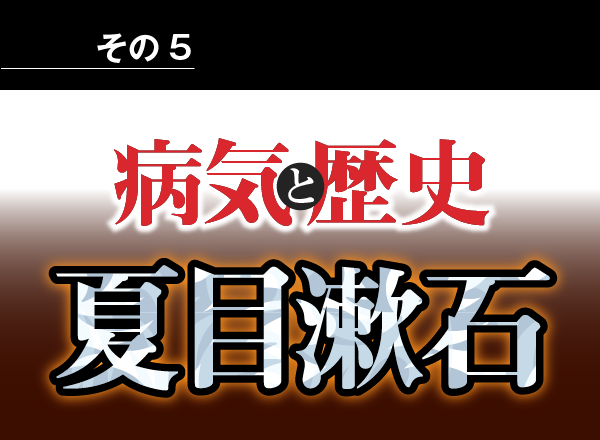
年をとるごとに病気がちに
明治を代表する国民的作家の夏目漱石は、慶応3年(1867)に名主夏目小兵衛の5男として江戸の牛込で生まれた。本名を金之助といい、数え2歳のときに塩原昌之助の養子となり幼年期を浅草で送った。
10歳のとき養父母が離婚したために生家に戻った。孤独で暗い子供時代を過ごしたようである。東京府立第1中学に入学するが中退し、二松学舎に入学した。漱石の漢詩の素養はこの時期に学んだ身につけたものである。
ところが、文明開化の時代に漢詩で身を立てることはむつかしく、成立学舎で英語を学び直した。明治17年(1884)に大学予備門に入学したが、ここでは英文学を専攻した。このとき、漱石は漢文よりも英文学を生涯の仕事と決めたようであった。しかし、東京帝 大英文科に進んだころから英文学への期待は失望へと変わっていった。 卒業後、高等師範学校で教鞭をとるようになった漱石は、ますます英文学への懐疑を深めていく。
18年(1895)年、高等師範学校を辞職した漱石は、愛媛の松山中学の英語教師になるという、当時の常識からしてまったく不可解な行動を起こした。都落ちである。周知であるが、この松山中学時代の経験がのちに傑作、「坊ちゃん」を生み出す礎となる。
松山でつくった〈大酔醒め来りて寒さ骨に徹し、余生養い得て山家に在り〉という漢詩を読むと、漱石が人生に対して懐疑を抱いているのがわかる。
翌19年(1896年)、熊本の第五高等学校へ移った漱石は、松山中学で知り合った正岡子規の影響から俳句を作っている。
明治33年(1900)、漱石は文部省の命令でイギリスに留学した。長い間苦しんだ英文学への懐疑を解決しようと猛勉強を始めたが、激しい神経衰弱に陥り、文部省への報告書を白紙のまま送ったことから、漱石が発狂したのではないかという噂が飛んだ。
36年(1903)に帰国後、東京帝大英文科講師として英文学概説の講義を行なったが、学生には難解で不評だった。一方、漱石の神経衰弱は帰国後も続き、しばしば幻聴に悩み一時、妻子とも別居している。高浜虚子のすすめで38年(1905)年に『ホトトギス』に発表した小説「吾輩は猫である」は、このときの苦しみを書いたものである。
「吾輩は猫である」によって小説家としての名前があがった漱石は、この年「倫敦塔」を書き、翌年には「坊っちゃん」と「草枕」を発表している。
こうした小説家としての活動は、大学教師との両立を困難にしていくことになった。40年(1907)に教職を辞して朝日新聞社に入社し、専属の小説家として『虞美人草』『それから』『門』など数々の小説を連載した。近代的知性に基づき、倫理的主題を追求する数多くの作品をものにし、近代文学に金字塔を打ち立てた。明治という動乱の時代、西洋文化に出会い、必死に自我を模索したといわれる。その追求の過程が、次々と作品に結実していき、進化していった。
漱石は、若い頃から体が弱く、年を重ねるごとに病気がちになり、肺結核、トラホーム、神経衰弱、痔、糖尿病、胃潰瘍などを発症した。天然痘にもかかった。若いころから胃弱で、作家活動に専念するようになってからは胃の障害にしばしば悩まされ、明治43年 (1910)に『門』を書きはじめたころの6月6日、長与胃腸病院で胃潰瘍と診断された。胃腸の専門病院として有名なこの大病院に18日に入院して加療したが、回復は思わしくなかった。
(続く)
文:東/茂由 ライター
1949年、山口県生まれ。早稲田大学教育学部卒。現代医学から東洋医学まで幅広い知識と情報力で医療の諸相を追求し、医療・健康誌、ビジネス誌などで精力的に取材・執筆。心と体、ライフスタイルや環境を含めて、健康と生き方をトータルバランスで多面的に捉えるその視点に注目が集まる。